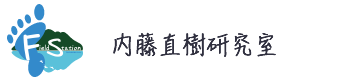今年もオープンゼミの季節がやってきました。
地域創生コースは研究室あたり原則的には定員4名、最大でも6名配属となっています。
自分が大学生活後半の2年間をどのように過ごすのか、どういう形で社会に羽ばたいていくのか、そのためにはどのゼミで勉強したら良いのか考える1ヶ月間ですね。ちなみに教員の方も、自分がどの人にどんなアシストをするのが良いか考えます。教員も学生もいろいろ思い悩む時期ですね。
内藤ゼミのオープンゼミは以下になります。
11/11(金)12:00-16:00
11/16(水) 8:40-12:30
11/18(金)12:00-16:00
予告したとおり、日程は希望してきた方の都合に合わせて変更しました。
いずれも前半は3年生2名による研究発表、後半は天気が良ければ野外での交流会です。3年生の研究発表に対して4年生が質問・コメントをおこなう形式になっています。3年生や4年生にゼミの様子や就活について聞く機会ですので、ふるってご参加ください。
また、オープンゼミ以外の日でも、内藤ゼミはいつもオープンなのでご参加ください。オープンゼミやそれ以外のゼミの参加希望者は内藤まで直接ご連絡ください。
私があまり好きでは無いのは「ズットモ」とか「ニコイチ」のような友達単位でゼミに入ろうとか考えること。たしかに友達同士だと、「イロイロ面倒くさい」ことを説明しなくても、価値観が似ているし、話も通じるのだと思います。が、地域創生コースの多くのゼミでは、「人間がおこなう諸活動」を言語化する作業をおこないます。ある現象を言葉で説明できるようになることを「理解」と言うのだと思いますし、「理解」することなしに、現状を変更する妥当な働きかけ(地域づくりだろうが社会問題の解決だろうが商品企画だろうが)はできないと思います。そう考えると、「ねぇ、そう思うよね?」、「そうそう」、「話がわかるなぁ」という関係は、「理解」への接近を遠ざけます。また、ゼミで関心を同じくする「顔見知り」と議論したりプロジェクトに取り組む経験を重ねると、それらの「顔見知り」もまた「友達」になっていきますから。そういった議論ができる友達を学友というのでしょうか。昭和時代の週刊少年ジャンプ風に言えば「強敵」と書いて友と読むような、そんな友達が出来ると良いですね。