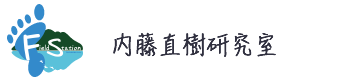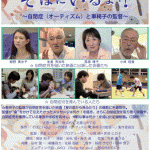院生のOくんと、自閉症という病とともに生きることのリアリティに向き合い続けた監督の晩年を描いたドキュメンタリー映画「そばにいるよ!~自閉症(オーティズム)と車椅子の監督」を鑑賞しました。
前半は監督の生き様に焦点をあてたメイキング映像風、後半は自閉症の子どもをもつ家族の暮らしを描いたドキュメンタリーになっていました。
Oくんは、自身もしばしば吃音に悩みながらも、吃音者のセルフヘルプグループでのたわいもない会話のやりとりに注目したユニークな卒業論文を執筆しました(興味がある方は、ゼミ生の研究テーマを参照してください)。なかなかよい卒論だったけど、そろそろ他の世界に飛び込んで、自らの経験を相対化したらいいような気がします。
先日のサマーキャンプでお目にかかった方々とも再会し、親切にしていただきました。ありがとうございました。
月別アーカイブ: 8月 2014
世界農業遺産・視察対応
世界農業遺産登録に関して、いつもお世話になっている農林水産省・中国四国農政局のみなさんの現地査察をご案内しました。それに加えて今回は徳島県の関連職員の方々がたくさん。大人数で東祖谷の集落にお邪魔したので、集落のみなさんが驚いていました。ご迷惑をおかけしました。
つるぎ町を出発時に、手近な地元の商店に入りました。店先のいい場所には、タカキビ、コキビ、ソバが売られています。雑穀食は地域の食文化に根付いています。
その後、東祖谷の雑穀畑やハチドウ(ニホンミツバチの養蜂箱)およびコエグロを裁断する様子を見ていただきました。
【動画】コエグロの草を裁断する様子↓
狩りガール第一号
ゼミ生のIさん(3年生)が狩猟免許試験を受験し、合格とのお言葉をいただいたとのことです。おめでとう!
内藤ゼミでは狩猟免許の講習もおこなっています。
徳島県でもシカ、イノシシ、サルなどの野生鳥獣による被害が深刻化していますが、柵の設置と猟友会による駆除という対症療法的な対策が中心です。
ところが野生鳥獣駆除の担い手である猟友会の平均年齢は、すでに70歳くらいになっています。この体制は10年はもたないであろうことが予想されます。山の自然に、新たなアクターが参入することが必要です。
岐阜県にあるNOP法人 メタセコイアの森の仲間たちさんでは、若い人びとによる新たな取り組みがおこなわれています。
猪鹿庁:http://inoshika.jp
9月25-26日には、今年度の実習生らと猪鹿庁の視察に行く予定です。
こうしたとりくみを、徳島県の文脈に合わせた形にローカライズできないか考えてみようと思います。
徳島県自閉症協会サマーキャンプin牟岐
心理学の先生方にお誘いいただき、徳島県自閉症協会さんが毎年運営されているサマーキャンプin牟岐に参加させていただきました。
目的は、昨年美波町・阿部集落の方々と学生とで開発した、津波災害時の避難支援器具を、自閉症用にローカライズすることです。それは緊急支援の現場にみられる、いつでも・どこでも使える支援器具(ユニバーサルな支援器具)開発という思想から、特定の文脈で有効な支援器具(ローカルな支援器具)開発という思想への転換です。つまり阿部の文脈にあわせてローカライズされたものを、自閉症という別の文脈に再ローカライズする作業をします。
夜に遊びを兼ねて支援器具の使い心地をモニターしてもらいました。
それはもちろん有意義だったけど、一泊二日で自閉症協会のみなさんと生活できたことがとても刺激になりました。コミュニケーションについて、そして支援のあり方について考えさせられました。
サマーキャンプの様子
http://d.hatena.ne.jp/tokusima80/
雑穀畑の贈り物
祖谷の雑穀をつくっているのは、いい感じのおじいさん、おばあさんたちでした。商業的には成功とはいえないけれど、生物多様性の維持に知らずに貢献している。つい忘れてしまうのですが、人間は生物としての身体を備えた存在ゆえの限界と特徴がある。生態人類学ことわざ−人はパンのみにて生きるにあらず。されどパン無くして生きることかなわず−。さー明日は何を食べて生きようか? No food No life!
みなさん、種をくださいという図々しいお願いに対して優しく応えてくださいました。ありがとうございます!いただいた種は、来年の春に試験区をつくって植えてみようと思います。広げよう四国山地の雑穀の輪!
製粉したシコクビエはウガリ(東アフリカでよく食べられている練り粥)、キビとヒエはゴハンにして、実習のときにでも食べようかしら?
祖谷の雑穀ジーンバンク
本日は祖谷の雑穀栽培の様子を見に行きました。「もうほとんど栽培されていない。これが最期の一件かも」と聞いていたのですが、その農家さんから友達の輪方式で雑穀栽培農家をたずね歩いたら、でるわでるわ。ヤツマタ(シコクビエ)、キビ(コキビ)、アワ、ヒエを栽培している農家の方々にお会いできました。農家の方によればシコクビエやキビ、アワ、ヒエの種子は、採種後2年以上たつと発芽率が落ちるということです。だから少しでも良いから毎年植え続けることが大事。時にはヒトリバエといって、自然にこぼれ落ちた種子から発芽した株も、採種用にとっておく。こうした農家の方の営みによって作物の遺伝的多様性が維持されているのですね。まさに生きたジーンバンクです。ちなみにシコクビエはアフリカ原産で、主に東アフリカの人びとの食をいまでも支えています。
ハチミツワークショップinつるぎ
つるぎ町一宇で、「徳大生と行く、夏休みハチミツ体験」を開催。ちょっと人数が多かったけど、何とか天気がもって良かった。ニホンミツバチのハチミツを収穫する際のポイントは、ミツの集め手が減らないように巣箱に残ったハチを可能な限り外に出してやること。
学習体験プロラムにするためには、まだまだ検討すべき課題がある。中学生の自由研究を2日で完成させるくらいのプログラムを用意すべきか?また、地域の方ともっと交流できる仕掛け作りが必要。
地元誌にとりあげられました
http://www.topics.or.jp/localNews/news/2014/08/2014_14084965599234.html